25.Jul.2025
防災の日とは?意味・由来・家庭でできる防災対策を徹底解説【9月1日は備える日】

こんにちは、まもるんパンスタッフです♪
毎年9月1日は「防災の日」です。
この日は、日本全国で防災についての意識を高め、災害に備えるための取り組みが行われる大切な日です。
しかし、日常生活の中で「なんとなく知っているけど、何をすればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、防災の日の由来や目的、各地での取り組み、そして家庭や個人でできる防災対策について詳しく解説します。
防災の日をきっかけに、いざというときに命を守るための行動を見直してみましょう!
防災の日の由来

防災の日は1960年に制定されました。
背景には、1923年(大正12年)9月1日に発生した「関東大震災」があります。
死者・行方不明者10万人以上という甚大な被害を出したこの地震は、日本の防災意識を大きく揺さぶりました。
この未曾有の災害を教訓に、国民の防災意識を高めるために制定されたのが「防災の日」です。
現在では、9月1日を中心とした「防災週間(8月30日~9月5日)」も設定され、全国の自治体や学校、企業で防災訓練や啓発イベントが行われています。
なぜ今、防災の日が重要なのか

日本は地震・台風・豪雨・津波・火山噴火など、多様な自然災害に見舞われる国です。
近年では、異常気象による線状降水帯の豪雨災害や、地震による広範囲な被害も増加傾向にあります。
例えば、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震、そして近年の豪雨災害など、私たちは常に「いつ、どこで」災害に遭うかわからない状況にあります。
こうした背景からも、防災の日はただの記念日ではなく、「備えを行動に移す日」としてますます重要性を増しています。
防災の日に行われる主な取り組み

各地の防災訓練
防災の日には、全国各地で大規模な防災訓練が行われます。
自治体によっては、実際に避難所へ向かう避難訓練や、津波を想定した高台への避難指導、炊き出し訓練などを実施しています。
防災無線やエリアメールなどの警報システムの動作確認も、この日に合わせて行われることが多いです。
学校や企業の訓練
学校では地震発生時の「身を守る行動」や、避難経路の確認、消火器の使い方などを学びます。
企業では、BCP(事業継続計画)に基づく訓練や安否確認システムの運用チェックが行われます。
これにより、災害発生時の混乱を最小限に抑える準備が整えられます。
メディアや公共機関による啓発活動
テレビやラジオ、インターネットでは、防災特集が組まれ、防災グッズの紹介や被災者の体験談、防災専門家によるアドバイスが広く紹介されます。
これらの情報は、日常の中では気付きにくい備えのヒントを与えてくれます。
家庭でできる防災の日の過ごし方

防災の日は、ただイベントを見たり参加したりするだけではなく、家庭や個人で具体的な行動に移すチャンスでもあります。
以下に、家庭でできる防災の日の取り組みをご紹介します。
1. 家族で避難場所と連絡手段の確認
災害時には、家族がバラバラの場所にいる可能性があります。
そのときの集合場所や避難所、連絡手段を事前に確認しておくことが重要です。
連絡が取れないことも想定し、災害用伝言ダイヤル(171)やSNSなどの代替手段も検討しましょう。
2. 非常持ち出し袋の点検
防災の日は、非常持ち出し袋の中身を見直す絶好のタイミングです。
食料や水、乾電池、薬、衛生用品、現金などを点検し、使用期限が切れていないかを確認しましょう。
季節に応じた衣類やマスクの準備も忘れずに。
3. 家の中の安全点検
家具の転倒防止対策はできていますか?
ガラス飛散防止フィルムは貼っていますか?
地震や台風に備え、家の中の危険な場所を見つけ、対策を施すことが重要です。
特に寝室や出入口付近は、早急な改善が必要な場所です。
4. 災害用グッズのローリングストック
食料や日用品を多めに買っておき、日常で使いながら一定の備蓄を維持する「ローリングストック」は、負担の少ない備え方として注目されています。
備蓄品の入れ替えタイミングを防災の日に設定するのも良い習慣です。
防災意識を高めるためにできること
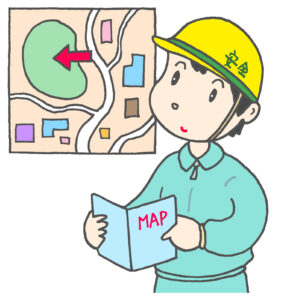
防災とは「特別な準備」ではなく、「日常に溶け込む習慣」です。
例えば、通勤経路や通学路にある避難場所の確認や、雨が強くなったときの気象情報チェック、SNSでの防災情報収集など、日頃から意識することで災害時の行動がスムーズになります。
また、地域の防災訓練に参加することで、近隣住民とのつながりを持ち、協力体制を築くことも可能です。
災害時に助け合うためには「顔の見える関係づくり」が重要です。
おわりに
防災の日は、私たち一人ひとりが「命を守るための行動」を見直すきっかけです。
地震や台風といった自然災害は避けられませんが、被害を最小限にする備えはできます。
年に一度の防災の日を「行動する日」と捉え、家族や地域とともに備えを強化しましょう。
日常に少しの工夫と意識を加えることで、いざというときに大切な命を守る力になります。

非常食として注目されている「まもるんパン」は、災害時にも安心して食べられる缶詰パンです!
2年間の長期保存が可能で、火や水が使えない状況でもそのまま開けてすぐに食べられる手軽さが魅力です。
しっとりとした食感で、小さなお子様から高齢の方まで食べやすく、味のバリエーションも豊富。
ローリングストックにも適しており、日常の中で食べながら備えることもできます。
防災の日をきっかけに、非常食の見直しとともに「まもるんパン」を取り入れて、家族の安心を備えましょう♪



